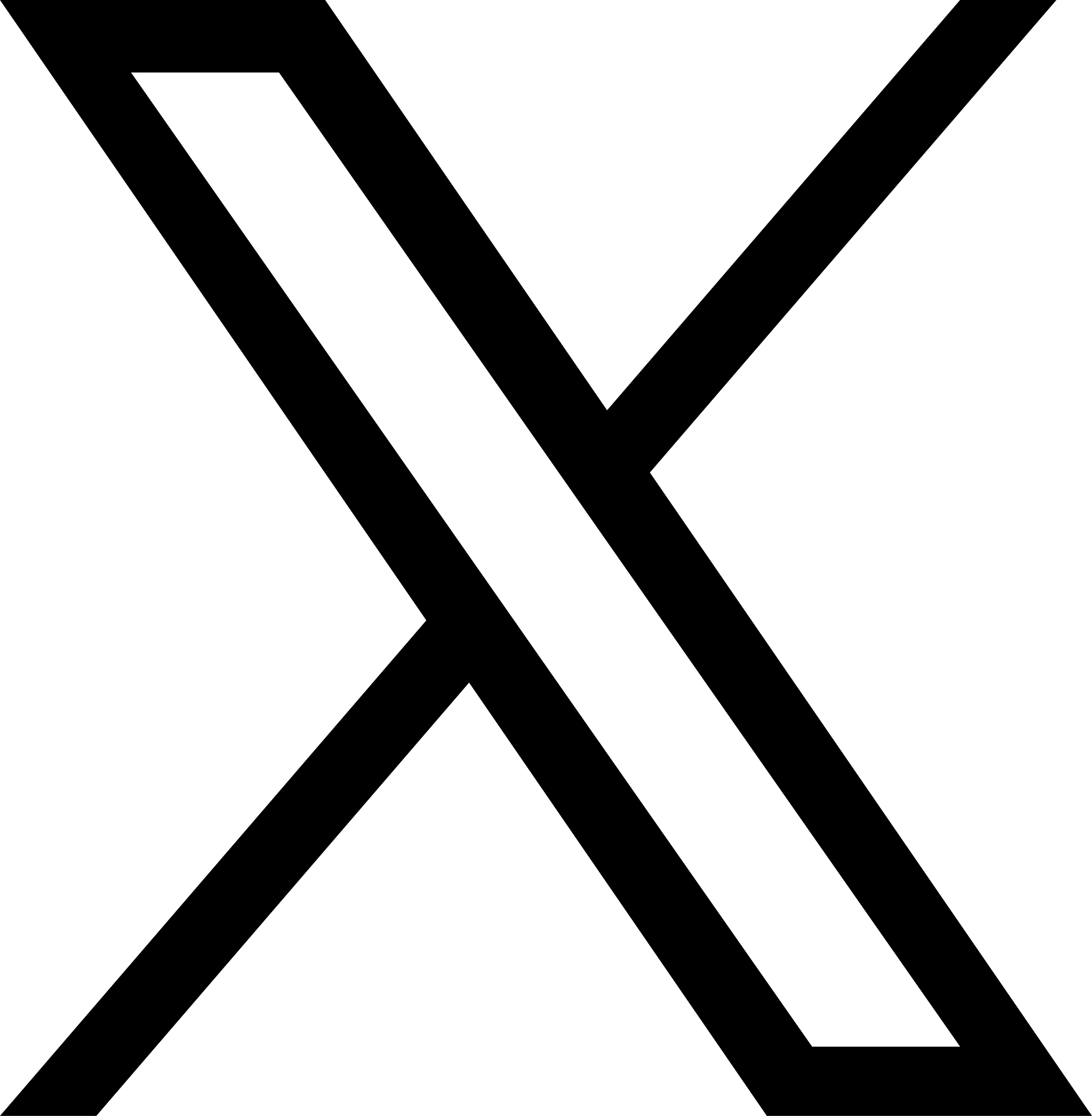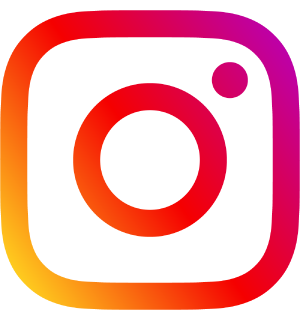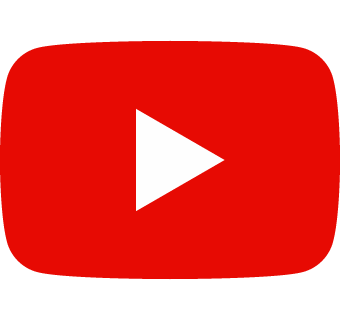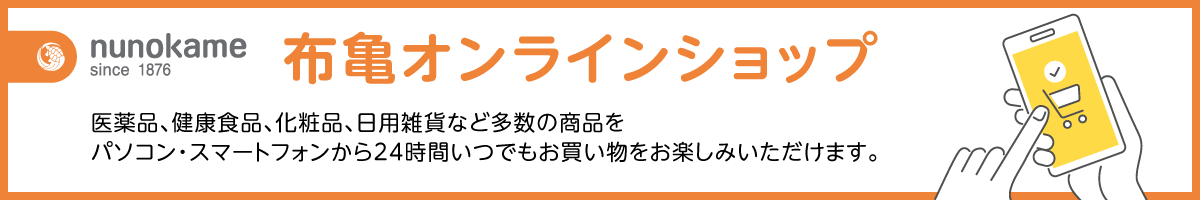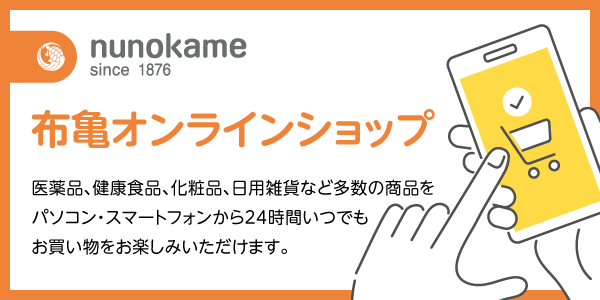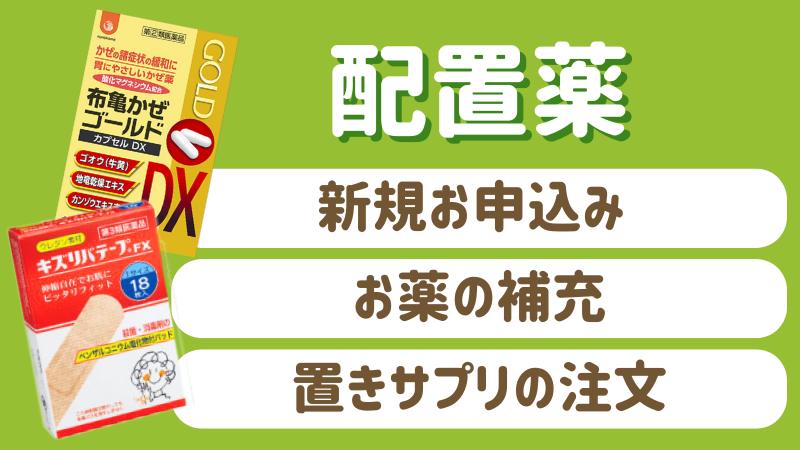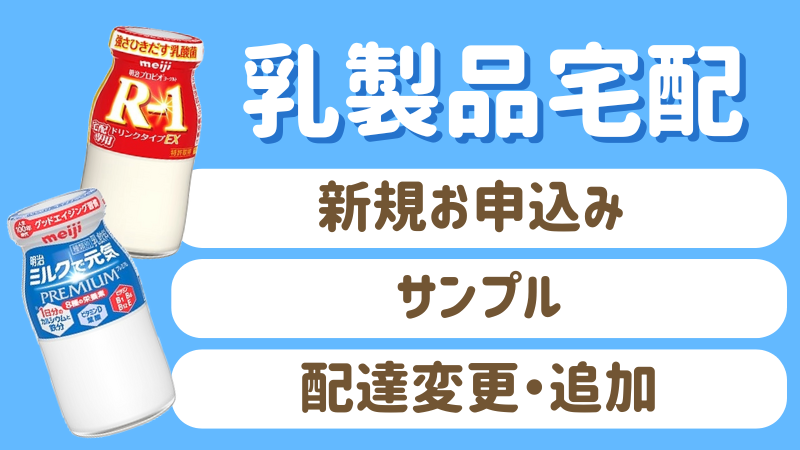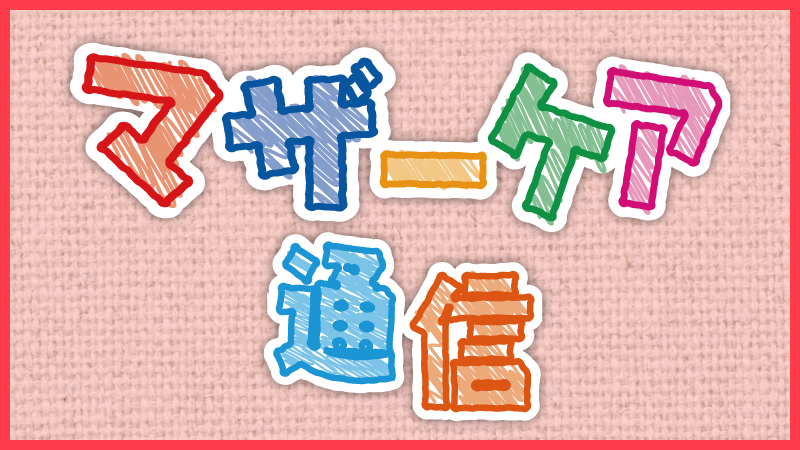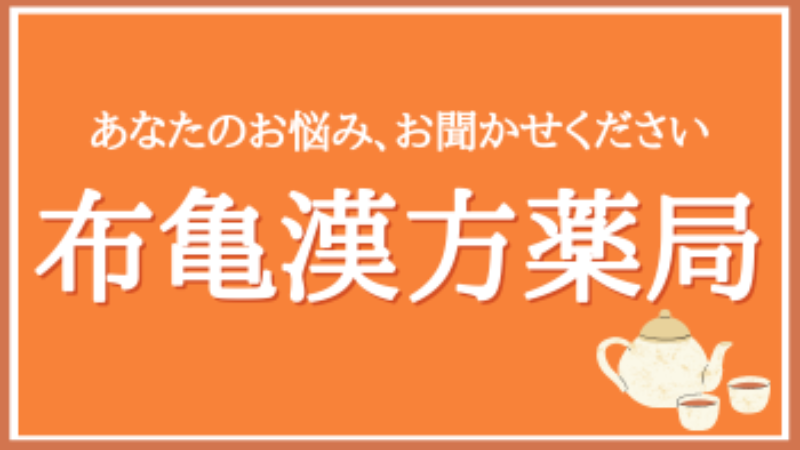お正月に飾られる「鏡餅」。どこかで見たことがあるけれど、どうしてお正月に欠かせないのか、意外と知らない人も多いのではないでしょうか?今回は鏡餅に込められた意味や由来を、少しだけ深掘りしてみましょう。

鏡餅の特徴的な形、2つのお餅を重ねたデザインには「年を重ね、幸せが続きますように」という願いが込められています。そして、上に乗せられた「橙(だいだい)」は、「代々(だいだい)家系や幸運が続くように」という願いを表しています。どの部分にも、家族や暮らしを大切に思う気持ちが込められているのですね。
名前の「鏡」は、昔の神聖な道具である「鏡」に由来しています。鏡餅は神様が宿る場所とされ、飾ることで神様を家にお迎えし、その加護を受けるという意味があります。

そして、お正月が終わると「鏡開き」という行事で鏡餅を食べます。包丁などの刃物を使わずに、木槌などで餅を割り、お雑煮やぜんざいなどにしていただくことで「神様の力を取り込む」と考えられています。刃物を避けるのは、「切る」ことが「縁起が悪い」とされているためですが、最近では真空パックに小分けされた個包装タイプの鏡餅が主流になっているため、固くなりすぎた餅を無理に割る手間が省け、安全性も大きく向上しました。

昔も今も、鏡餅は日本の伝統文化の中で家族や生活の安定を願う象徴として受け継がれています。今年のお正月は鏡餅を見ながらその深い意味に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?